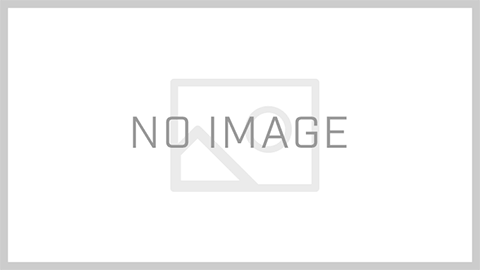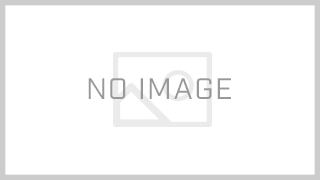ケープタウンで輸送業者に預け入れしたのが2019年8月22日。翌週には出港するという話だったが、実際出港したのが9月19日と1ヶ月遅れ。10月下旬に長い航路を経て日本へ戻ってきた。
受け入れは節約を兼ねて個人で引受手続きを行うことにした。業者に依頼するとおおよそ10諭吉が飛び去って行く…。
他のライダーさんの為にも流れと費用を記録として残します。
結論:お金がある人は業者に頼むべし
- 大型バイクをトラックの荷台から下ろすのは超危険
- 梱包されいる木箱の解体・廃棄に非常に困った
業者代行料金10万円を支払えるなら利用すべき。個人で引取る場合には第三者のお手伝いが必要となるし、大型バイクをトラックの荷台から下ろすのは超危険。又、梱包されていた木箱の廃棄先が見つからなくて非常に困りました。
日本へ向けての輸送手順と費用
| 輸出地 | 南アフリカ(Cape Town) |
|---|---|
| 輸入地 | 日本(Tokyo)港が沢山あり何処に入港するのか確認 |
| 梱包物 | テネレ、ヘルメット、パニアケース、トップケース、タンクバック |
| 総重量 | 404kg(グロス) |
- Econo Transにて日本輸送手続きを行う(日本円換算 10万円程度)
- 輸送業者にバイクを引き渡す(梱包内容を必ず書残す)
日本側での受取り手順
- Econo Transから”Bill of loading”(B/L)がPDFファイルで届く
- 日本の受入業者から”Arrival notice”(A/N)がPDFファイルで届く
- A/Nの内容確認をして支払いを済ませる
- 受入業者から”Delivery Order”(D/O)がPDFファイルで届く(印刷)
- インボイス&パッキングリストを印刷(中古価格要記載)
- 引受に必要となるトラックをレンタルする(2トン)
- 管轄税関に向かいD/Oを提出する(東京税関大井出張所)
- 荷受書類を貰って一時保管倉庫へ向かう(海貨センター)
- 倉庫で荷受書類を渡して引取る(トラックへ乗せる)
- 大型X線検査センターへ向かい検査を受ける(5分程度)
- 管轄税関へ戻り輸入内容をPCで入力作業(サポート有)
- 輸入許可通知書を受け取ることで無事に輸入手続き終了
南アフリカからの輸出入費用合計
合計額 = 155,300円
| Econo Trans | 約 100,000円 |
|---|---|
| 日本業者 | 約 35,000円 |
| 海貨センター | 1,300円(搬出代金) |
| 日産レンタカー | 15,000円 |
| ガソリン代金 | 4,000円 |
各種書類サンプル
輸出許可通知書
 輸出許可通知書
輸出許可通知書上記画像は鳥取の境港を出発する際に代行業者の上組様から貰った書類。これがとても大事な書類なので絶対に無くさないようにしてください。
船荷証券(B/L)
 船荷証券 B/L
船荷証券 B/LEcono Transから出港したタイミングで送られてくる書類となる。不思議なのだが、目的地詳細が不明だった。何処へ連絡しても到着する港が直近にならないと判明しない。
貨物到着案内 A/N
 船荷到着案内1
船荷到着案内1 船荷到着案内2
船荷到着案内2日本の受入業者からPDFファイルとして届く。支払い金額が明記されているので銀行振込する。入港する場所が決定してから「D/O」が発行される。
荷渡し指図書 D/O
 荷渡し指図書 D/O
荷渡し指図書 D/O日本の業者からD/Oが届くので税関での引受申請が出来る状態になる。
インボイス&パッキングリスト
こちらは日本から出発する際に作ったものを流用して作成してください。出発した時点よりも減ることはあっても増えることは稀と言われて調べられました。
個人でバイク輸入する例がないこともあり税関職員も困惑してました。結局、増えた理由としては「履かなくなったブーツやヘルメットを同封した為です」と説明したら関税を免除となりました。
ルールとして出発の際のリストに無いものは全て課税対象となるので注意が必要です。
参考になれば幸いです。
トラックから木箱を下ろすのが大変!
 梱包の木箱が壊れない
梱包の木箱が壊れない受取り倉庫近くの粗大ゴミセンターと産業廃棄物へ当たるが受入不可。粗大ゴミセンターは大田区民のみが利用可能。産廃業者は個人では受け入れ不可という回答だった。代行業者はそういった事情を知っていての値段設定なのだろう。

困った私はお手伝いいただく友人のご自宅で解体をお手伝い頂いた上、残った木箱は流用してくれて引き取ってくれることになった。
ラダーで下ろすのだが、今回の旅で一番の恐怖に襲われる。ラダーの角度が急だったこと、不慣れな位置でバイク操作したこと。更にラダーを下り始めたら修正ができないことが恐怖となった。
右手に右グリップ(フロントブレーキ)、左手はパニアステー。友人は最初左側にいて私と真逆な位置関係で支えてくれていた。
やり難いのか、今度は後方に下がって両手でパニアステーを支えてくれた。左側に誰もいないのがとても不安になった。今振り返ると、左側に立って両手でハンドルを握って下ろせばよかった。
転倒せずにバイクを下ろすことに成功。